「よし、今日こそ勉強するぞ!」と思っても、いつも三日坊主で終わってしまう。
そんな経験、誰にでもありますよね。わたしも、三日坊主のプロでした。
でも実は、「やる気」ではなく「科学的根拠に基づいた習慣化」こそが継続のカギなんです。
この記事では、心理学と脳科学に基づいて、勉強を無理なく続けるためのステップを解説します。
英語学習や資格勉強が続かないと悩む人も、これを読めば「やらなきゃ」から「やりたい」にきっと変わっていくはず!
習慣化の鍵は「やる気」ではなく「脳の仕組み」
私たちが勉強を続けられないのは、意志が弱いからだと思っていませんか?
「あぁ、また続かなかった。私はだめだ・・・」なんて思わないでください。
原因は、脳の性質に逆らっているからです。
脳はエネルギーを節約したがるため、新しい行動をすると「めんどくさい」と感じるようにできています。
そのため、急に1日2時間勉強しようとしても長続きしません。
まず意識すべきは「ハードルを極限まで下げる」こと。
「1時間勉強する」ではなく、「参考書を開く」「アプリを立ち上げる」「とりあえず机に座ってみる」など、“最小の一歩”から始めるのがコツです。

ドーパミンが生む「続けたくなる脳」
人間の脳は、達成感を感じるとドーパミンという快楽物質を出します。
このドーパミンが「もう一度やりたい」という気持ちを作るんです。
だから、勉強を続けたいなら「小さな成功体験」を積み重ねましょう。
「単語を3個覚えた」「アプリを開いた」「1分だけ復習した」——これで十分。
そのたびに「できた!」と感じることが、継続するエネルギーになり、脳がその快楽を求めて「またやろう」という状態につながります。
科学的に正しい「勉強習慣化の5ステップ」
トリガー(きっかけ)を決める
人は“特定の行動のあとに決まった動作をする”ようになると、無意識で続けられます。
たとえば、「朝コーヒーを飲んだら勉強を始める」「帰宅したら机に座って5分だけ単語帳を開く」など。
このように「〇〇のあとに〜する」という形で行動の連鎖(if-thenルール)を作るのが有効です。
ハードルを下げる
「気合が必要な行動」ほど続きません。
なんとなく日本人は、「気合」とか「根性」という言葉を使いがちですけどね。
教材をあらかじめ机に出しておく、スマホのホーム画面に学習アプリを置くなど、始めるまでの手間をできるだけ減らすことで自然に行動できます。
小さな成功を積み重ねる
「継続できた自分」を毎日確認することが大切です。
完璧を求めず、「今日は3分だけできた」「昨日より1問多く解けた」といった成功体験を積み上げましょう。
この繰り返しで、自己効力感(self-efficacy)が高まり、行動が自動化されていきます。
この自己効力感は、最近では人材育成の場面でも耳にすることが多くなった言葉です。
3分どころか、英語アプリを開いただけでも自分を褒めてください。
根拠のない自信でもいいです。「できた」ことに意識を集中してみましょう。
記録して「見える化」する
勉強した日をカレンダーにチェックしたり、アプリに記録するだけでもOK。
人間は「進歩が見える」とモチベーションが上がる生き物です。
おすすめは、学習トラッカーを使うこと。
例:Studyplus
学習記録帳
コソ勉
Now Then Time Tracking
ご褒美を設定する
勉強が終わったら、「好きな音楽を聴く」「スイーツを食べる」など、自分に小さなご褒美をあげましょう。
脳が「勉強=快感」と覚えるようになり、自然と勉強したくなります。
「21日で習慣化」は誤解?科学が示す本当の期間
「習慣は21日で身につく」という説をよく聞きますが、本当にその期間で習慣化するものなのでしょうか?ある研究では、平均66日(約2か月)で新しい行動が習慣化されることが分かっていますし、大きくこの二つの説があるようです。
つまり、長い方で考えると「最初の2か月」をどう乗り越えるかが最大のポイント。
一度サボっても大丈夫。「再開できた自分」を褒めることで、行動を途切れさせずに続けられます。
1日や2日サボってしまったことより、例えばその前に1週間続けたとしたら、その続けたことを褒めてください。
そんな“モチベが落ちたときの立て直し方”は、こちらの記事も参考にしてみてください。
習慣化を助ける心理テクニック3選
環境トリガーを固定する
勉強場所や時間を固定することで、脳が自動的に“勉強モード”になります。
たとえば「朝のカフェ=英語学習」「夜のデスク=資格勉強」など、行動と場所をリンクさせましょう。
公言して「社会的プレッシャー」を活かす
SNSで「今日もやった」と投稿するだけで、自然と継続しやすくなります。
人は“誰かに見られている”と思うとサボりにくくなる——これをアカウンタビリティ効果と呼びます。
ダイエットではこの手法を使って自分を奮起させる人をよく見かけますね。
「休む日」も計画に入れる
毎日完璧に続けようとすると、かえって挫折しやすくなります。
あらかじめ「週に1日は休む」と決めておくと、罪悪感が減り、リズムが安定します。
しんどくなったら休む、などふんわりした設定にすると、休んだ自分を責めたり、「今日もしんどいから仕方ない」とサボりがちになってしまうことも。
それを防ぐためにも、休みの計画を立てておくことは意外と重要です。

習慣化の実践プラン
まず、「勉強するトリガー」をひとつ決めましょう。
たとえば「朝起きて歯磨きしたら単語帳を開く」。
次に、「始めるハードルを下げる」工夫をします。
教材を見える場所に置く、スマホの通知で思い出させるなど。
そして、「小さな成功を記録」する。
例えばカレンダーに「やった日」をチェック。
たまったチェックマークを見ることで、自信が積み重なります。
最後に、「ご褒美」を設定。
「終わったら好きな動画を見る」「勉強後にコーヒーを飲む」「勉強したらペットと戯れる」など、心地よい習慣で締めることが継続の秘訣です。
まとめ|「努力」ではなく「設計」で続けよう
勉強を習慣にするために必要なのは、「根性」でも「やる気」でもありません。
脳の仕組みを利用した仕組みづくりです。
ポイントはこの3つ。
- 行動のハードルを下げる
- 小さな成功を積み上げる
- 継続を“見える化”する
この3つを意識するだけで、勉強は自然と生活の一部になります。
1日1分からでいい。
今日から「やる気がいらない勉強習慣」を作っていきましょう。
語学習を無理なく習慣化したいなら、スタディサプリENGLISHがおすすめ。
スマホ1台で、スキマ時間に“1日3分の英語習慣”を始めよう!
☞新日常英会話セットプランを無料で体験する

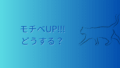
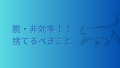
コメント